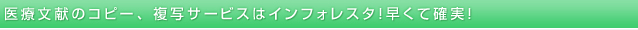=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ÒÇÉ1ÒÇæõ╣│þÖîµ▓╗þÖéÒü«µªéÞªü
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
µùѵ£¼ÒüºÒü»ÒÇüõ╣│þÖîÒü»ÕÑ│µÇºÒü«þÖîÒü«õ©¡Òüºµ£ÇÒééÕñÜÒüÅÒÇü
50µ¡│ÕëìÕ¥îÒéÆÒâöÒâ╝Òé»Òü½Õ╣┤Úûôþ┤ä4õ©çõ║║Òü«µû╣Òüîþ¢╣µéúÒüùÒüªÒüèÒéèÒÇü
ÒüØÒü«µò░Òü»ÕóùÕèáÒüùÒüªÒüäÒéïÒü¿ÒüäÒéÅÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
Òü¥ÒüƒÒÇüµéúÞÇàÒüòÒéôÒü«ÒüåÒüí3Õë▓Òü«µû╣ÒüîÕåìþÖ║´╝êÞ╗óþº╗´╝ëÒüÖÒéïÒü¿ÒüäÒéÅÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
õ╣│þÖîÒü«µ▓╗þÖéµ│òÒü»ÒÇüµëïÞíôÒÇüµö¥Õ░äþÀÜÒÇüÞû¼þë®Òü½ÒéêÒéèÒü¥ÒüÖÒüîÒÇü
ÒüôÒü«ÒüåÒüíÞû¼þë®þÖéµ│òÒü½Òü»ÒâøÒâ½ÒâóÒâ│þÖéµ│òÒÇü
ÕîûÕ¡ªþÖéµ│ò´╝êµèùþÖîÕëñÒÇüÕêåաɵ¿ÖþÜäµ▓╗þÖéÞû¼´╝ëÒüîÒüéÒéèÒÇü
þû¥µéúÒü«ÚÇ▓ÞíîÕ║ªÒÇüÒü¥ÒüƒÞíôÕëìÞíôÕ¥îÒü¬Òü®Òü½ÒéêÒéèÒÇü
µºÿÒÇàÒü¬Þû¼ÕëñÒüîþÁäÒü┐ÕÉêÒéÅÒüòÒéîÒüªµèòõ©ÄÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇé
µû░ÒüùÒüäÞû¼ÕëñÒééµ¼íÒÇàÒü¿Õ░ÄÕàÑÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒüîÒÇü
µ£¼Õ╣┤2µ£êÒü½ÒÇüµû░ÒüƒÒü½Òé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│ÒüîÚü®Õ┐£Òü«µïíÕñºÒüºµë┐Þ¬ìÒüòÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_089ÒÇæÒÇÅ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ÒÇÉ2ÒÇæÒé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│Òü½ÒüñÒüäÒüª
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Òé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│Òü»ÒâçÒé¬Òé¡ÒéÀÒéÀÒâüÒé©Òâ│Òü«Þ¬ÿÕ░Äõ¢ôÒüºÒÇü
ÒâîÒé»Òâ¼Òé¬ÒéÀÒâëþ│╗õ╗ú޼ص﫵èùÕëñÒüºÒüÖÒÇé
þ┤░Þâ×ÕåàÒüºÒâîÒé»Òâ¼Òé¬ÒâüÒâëÒüºÒüéÒéïõ║îÒâ¬Òâ│Úà©ÕÅèÒü│õ©ëÒâ¬Òâ│Úà©ÕîûÕÉêþë®Òü½õ╗úÞ¼ØÒüòÒéîÒÇü
õ╣│þÖîDNAÞñçÞú¢ÒéÆÚÿ╗Õ«│ÒüÖÒéïÕâìÒüìÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_090ÒÇæÒÇÅ
Õ║âþ»äÒü¬µèùÞà½þÿìµ┤╗µÇºÒéƵîüÒüíÒÇüµèùþÖîÕëñÒü¿ÒüùÒüªÕ╣àÕ║âÒüÅõ¢┐þö¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
1995Õ╣┤Òü½ÚûïþÖ║ÒüòÒéîÒüªõ╗ѵØÑÒÇü
ÚØ×Õ░Åþ┤░Þâ×Þé║þÖî´╝ê1999´╝ëÒÇüÞåÁÞçôþÖî´╝ê2001´╝ëÒÇüÞâåÚüôþÖî´╝ê2006´╝ëÒÇüÕ░┐ÞÀ»õ©èþÜ«þÖî´╝ê2008´╝ë
Òü¿ÒüØÒü«Úü®þö¿ÒéƵïíÕñºÒüùÒüªÒüìÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
õ╣│þÖîÒüºÒü»ÒÇü2003Õ╣┤Òü½ÒâòÒéúÒâ│Òâ®Òâ│ÒâëÒüºµë┐Þ¬ìÒüòÒéîÒüªõ╗ѵØÑ
2009Õ╣┤Òü«µÖéþé╣Òüº100Òé½Õø¢õ╗Ñõ©èÒüºµë┐Þ¬ìÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
µùѵ£¼ÒüºÒü»ÒÇüµ£¬µë┐Þ¬ìÞû¼Òü¿ÒüùÒüªõ©ÇÚâ¿õ¢┐þö¿ÒüòÒéîÒüªÒüìÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
õ╗èÕø×Òü«µë┐Þ¬ìÒéÆÕÅùÒüæÒüªÒÇüõ╣│þÖîÞ¿║þÖéÒé¼ÒéñÒâëÒâ®ÒéñÒâ│ÒüºÒééÒÇü
2007Õ╣┤þëêÒüºÒü»õ┐ØÚÖ║Úü®Õ┐£ÕñûÒü¿ÒüùÒüªþ┤╣õ╗ïÒüòÒéîÒüªÒüìÒüƒÒééÒü«ÒéÆÒÇü
2010Õ╣┤þëêÒüºÒü»õ©ëµ¼íõ╗ÑÚÖìÒü«ÕîûÕ¡ªþÖéµ│òÕëñÒü¿ÒüùÒüªµÄ¿ÕÑ¿ÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
õ©¡ÒüºÒééÒÇüÒâøÒâ½ÒâóÒâ│þÖéµ│òÒü½µäƒÕÅùµÇºÒüîÒü¬ÒüÅÒÇüHER-2ÚÖ░µÇºÒüºÒÇü
ÒüäÒéÅÒéåÒéïTriple NegativeÒü¿Õæ╝Òü░ÒéîÒéïþèµ│üÒüºÒü»ÒÇü
ÚçìÞªüÒü¬µ▓╗þÖéÞû¼Òü¿õ¢ìþ¢«ÒüÑÒüæÒéëÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_091ÒÇæ´¢×ÒÇÉIFB_093ÒÇæÒÇÅ
õ╣│þÖîÞ¿║þÖéÒé¼ÒéñÒâëÒâ®ÒéñÒâ│ÒüºÒüìÒüíÒéôÒü¿ÕÅûÒéèõ©èÒüÆÒéëÒéîÒéïÒü½Òü»ÒÇü
Òé¿ÒâôÒâçÒâ│Òé╣´╝êþºæÕ¡ªþÜäµá╣µïá´╝ëÒü«þó║þ½ïÒü¿ÒüäÒüåÚüÄþ¿ïÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
µèùþÖîÕëñÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕñÜÕëñõ¢Áþö¿ÒüîÞ®ªÒü┐ÒéëÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕñÜÒüÅÒÇü
ÕìÿÕëñÒéêÒéèÕè╣µ×£Òü«õ©èÒüîÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÕñÜÒüäÒüôÒü¿ÒüïÒéëÒÇü
µºÿÒÇàÒü¬þÁäÒü┐ÕÉêÒéÅÒüøÒüºÒü«Þç¿Õ║èÞ®ªÚ¿ôÒüîÞíîÒéÅÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
õ©¡ÒüºÒéé2005Õ╣┤Òü½ÞíîÒéÅÒéîÒüƒ
ÒâæÒé»Òâ¬Òé┐Òé»Òé╗Òâ½ÕìÿÕëñÒü¿ÒâæÒé»Òâ¬Òé┐Òé»Òé╗Òâ½´╝ïÒé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│Òü«µ»öÞ╝âÒéÆÞíîÒüúÒüƒ
Òâ®Òâ│ÒâÇÒâáÕîûµ»öÞ╝âÞ®ªÚ¿ôÒüºÒü»ÒÇüÕ¥îÞÇàÒü«Õè╣µ×£Òüîõ©èÕø×ÒéïÒüôÒü¿Òüîþñ║ÒüòÒéîÒÇü
þ▒│Õø¢ÒüºFDAÒü«Þ¬ìÕÅ»ÒéÆÕÅùÒüæÒéïµá╣µïáÒü¿ÒééÒü¬ÒéèÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_094ÒÇæÒÇÅ
Òü¥Òüƒµùѵ£¼Õø¢ÕåàÒüºÒééþ¼¼IIþø©Òü«Þç¿Õ║èÞ®ªÚ¿ôÒüîÕ«ƒµû¢ÒüòÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇü
2010Õ╣┤3µ£êÒü½þÁéõ║åÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
´╝êClinicaltrials.govÒÇÇÞç¿Õ║èÞ®ªÚ¿ôþò¬ÕÅÀNCT00334802ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_095ÒÇæÒÇÅ
ÒüèÒéêÒü│NCT00191269ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_096ÒÇæÒÇÅ´╝ë
Òü¥ÒüƒÒüØÒü«þùçõ¥ïÒééÕá▒ÕæèÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_097ÒÇæ´¢×ÒÇÉIFB_100ÒÇæÒÇÅ
Þ┐æÕ╣┤ÒÇüÒüòÒéëÒü½Triple NegativeÒü«þùçõ¥ïÒü½Õ»¥ÒüùÒüªÒÇü
Gemcitabine´╝ïCarboplatinÒü½ÕèáÒüêÒüª3Õëñþø«Òü¿ÒüùÒüªPARP1Úÿ╗Õ«│ÕëñÒüºÒüéÒéï
BS201ÒéÆÕèáÒüêÒüƒµ▓╗þÖéµ│òÒééÕç║ÒüªÒüìÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒÇÄÕÅéÞÇâµûçþî«´╝ÜÒÇÉIFB_101ÒÇæ´¢×ÒÇÉIFB_102ÒÇæÒÇÅ
õ╣│þÖîÒüºÒü»ÒÇüÕñûþºæþÜäµ▓╗þÖéÒéäÞû¼þ뮵▓╗þÖéÒü«õ©Çµ¼íµ▓╗þÖéÒüºÕÑÅÕèƒÒüøÒüÜÒÇü
Þ╗óþº╗µÇºÒü½ÕåìþÖ║ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒü½Òü»µ▓╗þÖéÒüîÕø░ÚøúÒü¿Òü¬ÒéïÕá┤ÕÉêÒééÕñÜÒüÅÒÇü
ÒüºÒüìÒéïÒüáÒüæÚòÀµ£ƒÒü½ÒéÅÒüƒÒéèµéúÞÇàÒüòÒéôÒü«QOLÒéÆþ¡µîüÒüùÒü¬ÒüîÒéë
ÚüÄÒüöÒüùÒüªÒééÒéëÒüåÒüôÒü¿ÒüîÞ¬▓ÚíîÒü¿Òü¬ÒüúÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒüåÒüùÒüƒÒé▒Òâ╝Òé╣ÒüºÒü»ÒÇüÒéêÒéèÕ╗ÂÕæ¢Õè╣µ×£Òü«Ú½ÿÒüäÞû¼ÕëñÒü«Úü©µè×Òüî
ÒüèÒüôÒü¬ÒéÅÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüÒüôÒüåÒüùÒüƒõ©ëµ¼íõ╗ÑÚÖìÒü«Þû¼þë®þÖéµ│òÒü½ÒÇü
µèùþÖîÕëñÒü¿ÒüùÒüªÒü«Òé╣ÒâÜÒé»ÒâêÒâ½Òü«Õ║âÒüäÒé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│Òüî
Úü©µè×ÞéóÒü«õ©ÇÒüñÒü¿ÒüùÒüªþÖ╗Õá┤ÒüùÒüƒÒüôÒü¿Òü»µ¡ôÞ┐ÄÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
Òé▓ÒâáÒéÀÒé┐ÒâôÒâ│Òü½ÒéêÒéïõ╣│þÖîÒü«õ©ëµ¼íµ▓╗þÖé