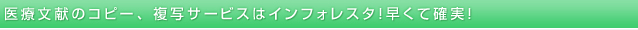зҸҫеңЁж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҖҒжҖҘжҖ§гӮ„ж…ўжҖ§гҒ®еҝғдёҚе…ЁгӮ’дҪөгҒӣгҒҰ160дёҮдәәпҪһ250дёҮдәәгҒ®
жӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҝғдёҚе…ЁгҒҜеҝғзӯӢгҒ®еҸҺзё®еҠӣгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒ
гҒқгҒ®зөҗжһңиЎҖжөҒйҮҸгҒҢеў—еҠ гҒ—дҪ“ж¶ІгҒ®иІҜз•ҷгӮ’гҒҚгҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒе…Ёиә«гҒҶгҒЈиЎҖзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒзү№гҒ«дёӢиӮўгҒ«жө®и…«гҒҢеҮәгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгӮҖгҒҸгҒҝгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҝғдёҚе…ЁгҒ®жІ»зҷӮгҒ«гҒҜгҖҒеҝғзӯӢгҒ®ж©ҹиғҪдҪҺдёӢгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еј·еҝғеүӨгҒ§гҒӮгӮӢ
гӮёгӮ®гӮҝгғӘгӮ№гҒӘгҒ©гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ
жө®и…«гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҲ©е°ҝеүӨгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ1гҖ‘гғҲгғ«гғҗгғ—гӮҝгғі(Tolvaptan)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гғҲгғ«гғҗгғ—гӮҝгғігҒҜгҖҒжҠ—еҲ©е°ҝгғӣгғ«гғўгғігҒ§гҒӮгӮӢгғҗгӮҪгғ—гғ¬гӮ·гғіV2еҸ—е®№дҪ“гҒёгҒ®
зөҗеҗҲгӮ’йҒёжҠһзҡ„гҒ«йҳ»е®ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ©е°ҝгҒҷгӮӢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҝғдёҚе…ЁгҒ«гӮҲгӮҠдҪ“ж¶ІиІҜз•ҷгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдҪ“гҒ®йӣ»и§ЈиіӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢеҙ©гӮҢгҖҒ
зү№гҒ«дҪҺгғҠгғҲгғӘгӮҰгғ иЎҖз—ҮгҒҢиө·гҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгғҲгғ«гғҗгғ—гӮҝгғігҒҜ
дҪ“еҶ…гҒ®йҒҺеү°гҒӘж°ҙеҲҶгҒ®гҒҝгӮ’жҺ’жі„гҒҷгӮӢгҖҢж°ҙеҲ©е°ҝгҖҚеүӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҲ©е°ҝеүӨгҒЁгҒ—гҒҰ
гӮҲгҒҸз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгғ«гғјгғ—еҲ©е°ҝеүӨгҒ§гҒӮгҒҫгӮҠеҠ№жһңгҒ®гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгӮ„гҖҒ
гҒқгӮҢгӮүгҒЁдҪөз”ЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_045гҖ‘пҪһгҖҗIFI_050гҖ‘гҖҸ
2009е№ҙ5жңҲгҒ«зұіеӣҪгҒ§SIADHпјҲжҠ—еҲ©е°ҝгғӣгғ«гғўгғідёҚйҒ©еҲҮеҲҶжіҢз—ҮеҖҷзҫӨпјүгҒ®
жІ»зҷӮи–¬гҒЁгҒ—гҒҰжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒеҗҢе№ҙ8жңҲгҒ«гҒҜ欧е·һгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢдё–з•ҢгҒ®31гғ¶еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒ2010е№ҙ10жңҲгҒ«гҖҒгғ«гғјгғ—еҲ©е°ҝи–¬зӯүгҒ®д»–гҒ®еҲ©е°ҝи–¬гҒ§
еҠ№жһңдёҚеҚҒеҲҶгҒӘеҝғдёҚе…ЁгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҪ“еҶ…иІҜз•ҷгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲ©е°ҝеүӨгҒЁгҒ—гҒҰжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
(еҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢжүҝиӘҚжғ…е ұгҖҖhttp://bit.ly/iMZPDo)
гҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬еҫӘз’°еҷЁеӯҰдјҡгҒ®гҖҢж…ўжҖ§еҝғдёҚе…ЁжІ»зҷӮгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі(2010е№ҙж”№иЁӮзүҲ)гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒ
2005е№ҙзүҲгҒ«гҖҢзҙ”зІӢгҒӘж°ҙеҲ©е°ҝгӮ’дҝғйҖІгҒ—гҖҒйӣ»и§ЈиіӘз•°еёёгӮ„RAAзі»гҒ®иіҰжҙ»еҢ–гӮ’жқҘгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„
гғҗгӮҪгғ—гғ¬гғғгӮ·гғійҳ»е®іи–¬гҒҢдҪҝз”ЁеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёҖж–ҮгҒҢд»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
(ж—Ҙжң¬еҫӘз’°еҷЁеӯҰдјҡгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҖҖhttp://bit.ly/kxHMXf)
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж №жӢ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢEVERESTи©ҰйЁ“гҒ§гҒҷгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ2гҖ‘ EVERESTи©ҰйЁ“гҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®еҫҢгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®иҮЁеәҠи©ҰйЁ“
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
EVERESTи©ҰйЁ“гҒҜгҖҒж…ўжҖ§еҝғдёҚе…ЁжӮЈиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғҲгғ©гғҗгғ—гӮҝгғігҒ®еҠ№жһңгӮ’
иӘҝгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҒеӨҡеӣҪзұҚгҖҒеӨҡж–ҪиЁӯгҒ«гӮҲгӮӢгғ—гғ©гӮ»гғңгӮ’еҜҫз…§гҒЁгҒ—гҒҹ
дәҢйҮҚзӣІжӨңи©ҰйЁ“гҒ§гҖҒ2003е№ҙгҒӢгӮү2006е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
(ClinicalTrials.govгҒ®жІ»йЁ“з•ӘеҸ·гҖҖNCT00071331)
гҒқгҒ®зөҗжһңгҒҜгҖҒдҪ“йҮҚжёӣе°‘гҖҒжө®и…«гҖҒе‘јеҗёзҠ¶ж…ӢгҒ®ж”№е–„гҒ®еәҰеҗҲгҒ„гҒҢ
гғҲгғ©гғҗгғ—гӮҝгғізҫӨгҒ§жңүж„ҸгҒ«е„ӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҹӯжңҹгҒ®е ҙеҗҲгҒ§гҖҒй•·жңҹжҠ•дёҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜ
жңүж„ҸгҒӘе·®гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_051гҖ‘пҪһгҖҗIFI_054гҖ‘гҖҸ
ж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§гӮӮгғ—гғ©гӮ»гғңгӮ’еҜҫз…§гҒЁгҒ—гҒҹдәҢйҮҚзӣІжӨңи©ҰйЁ“гҒҢгҖҒ
2007е№ҙгҒӢгӮү2009е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
2009е№ҙгҒ®ж—Ҙжң¬еҫӘз’°еҷЁеӯҰдјҡгҒ§гғҲгғ«гғҗгғ—гӮҝгғігҒҢиЎҖең§гӮ„йӣ»и§ЈиіӘгҒ«
з•°еёёгӮ’жқҘгҒҷгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒе®үе…ЁгҒ«жө®и…«гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖҒ
гҒЁзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
(ClinicalTrials.govгҒ®жІ»йЁ“з•ӘеҸ·гҖҖ
NCT00462670, NCT00525265, NCT0544869)
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_055гҖ‘пҪһгҖҗIFI_056гҖ‘гҖҸ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүй•·жңҹжҠ•дёҺгҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ
гҖҢзү№гҒ«й•·жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮӢдҪҺгғҠгғҲгғӘгӮҰгғ иЎҖз—ҮгҒ®жӮЈиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ
ж…ҺйҮҚгҒӘжІ»зҷӮгҒЁжіЁж„Ҹж·ұгҒ„йӣ»и§ЈиіӘгҒ®гғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ®
жҢҮж‘ҳгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_057гҖ‘гҖҸ
еҝғдёҚе…ЁгҒ®еҲ©е°ҝеүӨ гғҲгғ«гғҗгғ—гӮҝгғі