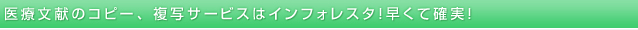=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ1гҖ‘гӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гҒ®жІ»зҷӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒгӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гҒ®жӮЈиҖ…ж•°гҒҜеӨҡгҒҸгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ家еәӯгҒ§
д»Ӣиӯ·гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҫгҒ§еҗ«гӮҒгҒҰ140дёҮдәәгҒӢгӮү170дёҮдәәзЁӢеәҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
85жүҚд»ҘдёҠгҒ®й«ҳйҪўиҖ…гҒ§гҒҜ25пј…гҒ«дҪ•гӮүгҒӢгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жІ»зҷӮжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒйҖІиЎҢгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢи–¬зү©зҷӮжі•гҒҢдё»гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гғүгғҚгғҡгӮёгғ«(Donepezil)гҒ—гҒӢжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒ
е”ҜдёҖгҒ®жІ»зҷӮи–¬гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒ欧зұігҒ§гҒҜж–°и–¬гҒ®й–Ӣзҷәгғ»жүҝиӘҚгҒҢйҖІгҒҝгҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_034гҖ‘пҪһгҖҗIFI_036гҖ‘гҖҸ
ж—Ҙжң¬зҘһзөҢеӯҰдјҡгҒӘгҒ©гҒ®дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—Үз–ҫжӮЈжІ»зҷӮгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі2010гҖҚгҒ§гӮӮгҖҒ
гғүгғҚгғҡгӮёгғ«гҒЁдёҰгӮ“гҒ§гҖҒгӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҖҒгғӘгғҗгӮ№гғҒгӮ°гғҹгғігҖҒгғЎгғһгғігғҒгғігҒ®
4еүӨгҒҢжІ»зҷӮгҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҒЁгғЎгғһгғігғҒгғігҒҢ2011е№ҙ1жңҲгҒ«ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ2гҖ‘гӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғіпјҲGalantamineпјү
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғіпјҲиҮӯеҢ–ж°ҙзҙ й…ёгӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғіпјүгҒҜгҖҒи»ҪеәҰгҒӘгҒ„гҒ—дёӯзӯүеәҰгҒ®
гӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гҒ®иӘҚзҹҘж©ҹиғҪгҒ®з—…зҠ¶йҖІиЎҢгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
и„іеҶ…зҘһзөҢдјқйҒ”зү©иіӘгҒ§гҒӮгӮӢгӮўгӮ»гғҒгғ«гӮігғӘгғігӮ’еҲҶи§ЈгҒҷгӮӢгӮігғӘгғігӮЁгӮ№гғҶгғ©гғјгӮјгӮ’
йҳ»е®ігҒ—(AchEI)гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гғӢгӮігғҒгғіеҸ—е®№дҪ“гӮ’еҲәжҝҖгҒ—гҒҰгӮўгӮ»гғҒгғ«гӮігғӘгғігҒ®ж”ҫеҮәгӮ’
дҝғгҒ—пјҲAPLдҪңз”ЁпјүгҖҒгӮўгӮ»гғҒгғ«гӮігғӘгғігҒ®жҝғеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒеӯҰзҝ’гӮ„иЁҳжҶ¶гҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’
ж”№е–„гҒӘгҒ„гҒ—гҒҜйҖІиЎҢгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢдҪңз”ЁгӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_037гҖ‘пҪһгҖҗIFI_038гҖ‘гҖҸ
гғӢгӮігғҒгғіеҸ—е®№дҪ“еҲәжҝҖдҪңз”ЁгҒҜгҖҒгӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҒ«зү№жңүгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒ
гғүгғҚгғҡгӮёгғ«гҒ«гҒҜз„ЎгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒзҘһзөҢзҙ°иғһжӯ»гҒ«еҜҫгҒ—дҝқиӯ·и–¬гҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҖҒз—…ж…ӢгҒ®йҖІеұ•гҒ«гҒҹгҒ„гҒҷгӮӢ
жҠ‘еҲ¶еҠ№жһңгӮӮжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_039гҖ‘пҪһгҖҗIFI_040гҖ‘гҖҸ
1999е№ҙгҒ«гӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҖҒ2000е№ҙгҒ«ж¬§е·һгҒ§гҖҒ
2001е№ҙгҒ«гҒҜзұіеӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«70гғ¶еӣҪд»ҘдёҠгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2004е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«з¬¬IIIзӣёи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
иҝҪеҠ и©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢ2008е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«зөӮдәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲClinicalTrials.govгҖҖиҮЁеәҠи©ҰйЁ“з•ӘеҸ·гҖҖNCT00814801пјү
гҒ“гҒ®зөҗжһң2011е№ҙпј‘жңҲгҒ®жүҝиӘҚгҒ«гҒ„гҒҹгҒЈгҒҹиЁігҒ§гҒҷгҖӮ
еҜ©жҹ»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®и©ігҒ—гҒ„жғ…е ұгҒҜеҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢгҒ®
гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
http://tinyurl.com/3cbhyy9
гӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§еҲқгӮҒгҒҰгӮӘгӮӘгғһгғ„гғҰгӮӯгӮҪгӮҰпјҲеҲҘеҗҚгӮ№гӮәгғ©гғігӮ№гӮӨгӮ»гғіпјү
з”ұжқҘгҒ®гӮўгғ«гӮ«гғӯгӮӨгғүгӮ’еҚҳйӣўгҒ—гҒҰиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ§еҗҲжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜеҢ–еӯҰеҗҲжҲҗгҒ«гӮҲгӮҠиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_041гҖ‘пҪһгҖҗIFI_042гҖ‘гҖҸ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ3гҖ‘й•·жңҹдәҲеҫҢгҒ«гӮӮжңҹеҫ…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜйҖІиЎҢжҖ§гҒ®з—…ж°—гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒ
жІ»зҷӮгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜз—…ж°—гҒ®йҖІиЎҢгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢзӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зӮ№гҖҒгӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҒҜй•·жңҹзҡ„гҒӘеҠ№жһңгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_043гҖ‘гҖҸ
й•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒёгҒ®д»Ӣиӯ·гҒҜгҖҒ家ж—ҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
гӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғігҒ®й«ҳз”ЁйҮҸжҠ•дёҺгҒ§д»Ӣиӯ·иҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒҢжңүж„ҸгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮӢ
е ұе‘ҠгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_044гҖ‘гҖҸ
гӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гҒ®ж–°гҒ—гҒ„жІ»зҷӮи–¬ гӮ¬гғ©гғігӮҝгғҹгғі