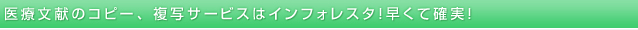=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
【1】アルツハイマー型認知症の治療
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
認知症の患者数は世界的にも爆発的に増加しており、
世界で2,430万人とされ、日本でも現在200万人を超え、
2025年には330万人に達するものと予想されています。
85才以上の高齢者では3~4人に1人が認知症であるといわれています。
この認知症の中でも60~75%を占めているのが
アルツハイマー型の認知症患者です。
記憶障害などの中核症状と、徘徊などの行動異常を来す周辺症状とがあり、
進行型で完治は難しいとされています。
従って治療の中心も、中核症状の進行を遅らせ、
周辺症状による家族などの社会的な負担を軽減することに
重点がおかれています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
【2】メマンチン(Memantine)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2011年に入り、いくつかの治療薬が承認・発売されるようになりました。
なかでも、メマンチンと同時に承認された
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるガランタミンにつきましては、
すでに2011年6月8日号の本解説で紹介しています。
メマンチンは、こうしたアセチルコリンエステラーゼ阻害とは
異なる薬理作用を持つもので、独自な作用を持っています。
『参考文献:【IFI_071】~【IFI_072】』
メマンチンは、アダマンタン誘導体を有する
非競合的NMDA(N-methyl-D-asparate)受容体阻害薬です。
刺激伝脱物質であるグルタミン酸の受容体の一つであるNMDAは
海馬に多く存在し、記憶の増強作用があります。
これが減少することにより記憶障害(認知症)が発症するとされています。
グルタミン酸受容体が異常蛋白により刺激され、神経細胞に毒性を
持つようになりますが、この受容体にメマンチンが結合すると
グルタミン酸の興奮毒性を阻止し、細胞内への過剰なCaイオンの流入を
阻害して神経細胞の障害や細胞死を防ぐという薬理作用を持っています。
『参考文献:【IFI_073】~【IFI_077】』
神経保護作用についても報告されています。
『参考文献:【IFI_078】』
メマンチンは1960年代に低血糖の薬剤として開発されましたが、
薬効が証明されず、改めて1972年にパーキンソン病の治療薬として
ドイツで再発見されました。
ドイツや米国で抗パーキンソン薬として承認されましたが、
やはりあまり効果が無く、再度忘れられてしまいますが、
1990年代にアダマンタン化合物の一つとして
アルツハイマー型認知症治療薬としての大規模臨床試験などが行われました。
その結果中等度~高度のアルツハイマー型認知症の
病状進行を遅らせる効果が示されました。
『参考文献:【IFI_079】』
これを受けて2002年に欧州で、2003年には米国で承認されるに至りました。
エビデンスを示すレビューとして名高いコクランの
システマティックレビューも作成され、中等度~高度のアルツハイマー型
認知症に効果のあることが示されています。
このレビューは、診療ガイドラインをインターネットで公開している
Mindsのコクランレビュー欄で、日本語の抄録を読むことができます。
(http://bit.ly/qfIJM9)
2009年には、日本神経学会など4学会が、
早期承認を求めて嘆願書を作成しています。
これらから、2011年1月に日本でも承認され、
3月には製品として販売されています。
(医薬品医療機器総合機構承認情報は http://bit.ly/p21oPT)
国内での臨床試験も進行し、『参考文献:【IFI_080】』
日本神経学会などの作成する「認知症疾患治療ガイドライン」でも、
従来用いられていたドネペジルや、同時に承認されたガランタミンなどと
並んで、推奨度Aとしています。
ドネペジルとの併用が効果的です。
『参考文献:【IFI_081】』
周辺症状への効果も期待でき、行動・心理症状評価スコアの
改善を認めたとする報告もあります。
『参考文献:【IFI_082】』
家族など介護者の負担が軽減する可能性もあり、その点でも期待されます。
アルツハイマー型認知の新しい症治療薬 メマンチン