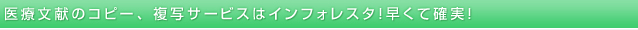йӘЁзІ—й¬Ҷз—ҮгҒҜгҖҒйӘЁеҜҶеәҰгӮ„йӘЁиіӘгҒӘгҒ©гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҖҒйӘЁгҒҢи„ҶејұгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ
йӘЁжҠҳгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮӢе…Ёиә«зҡ„гҒӘйӘЁз–ҫжӮЈгҒ§гҒҷгҖӮ
еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз ҙйӘЁзҙ°иғһгҒҢжҙ»жҖ§еҢ–гҒҷгӮӢй–үзөҢеҫҢгҒ®й«ҳйҪўгҒ®еҘіжҖ§гҒ«
еҘҪзҷәгҒҷгӮӢд»–гҖҒгӮ№гғҶгғӯгӮӨгғүеүӨгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гӮ„гҖҒй«ҳиЎҖең§гӮ„и„ӮиіӘз•°еёёз—ҮгҖҒзі–е°ҝз—…
гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҹжҙ»зҝ’ж…Јз—…гҒЁгӮӮй–ўйҖЈгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йӘЁеҜҶеәҰгҒ«гӮҲгӮӢиЁәж–ӯгҒ§гҒҜгҖҒ50жүҚд»ҘдёҠгҒ®еҘіжҖ§гҒ®30.6пј…гҖҒз”·жҖ§гҒ®12.4пј…гҖҒ
еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰ1380дёҮдәәгҒ®жӮЈиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁжҺЁиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_058гҖ‘гҖҸ
FRAXгҒЁгҒ„гҒҶйӘЁжҠҳгғӘгӮ№гӮҜи©•дҫЎеҹәжә–гҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®иЁәж–ӯеҹәжә–гӮӮзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
йӘЁжҠҳдәҲйҳІгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж—©жңҹгҒ®жІ»зҷӮй–Ӣе§ӢгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_059гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒгҒқгҒ®жІ»зҷӮгҒ«гҒҜйӘЁеҗёеҸҺжҠ‘еҲ¶еүӨгҒ§гҒӮгӮӢгғ“гӮ№гғӣгӮ№гғӣгғҚгғјгғҲ
(Bisphosphonate)гҒҢдё»гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘йӘЁеҪўжҲҗдҝғйҖІеүӨгҒ§гҒӮгӮӢ
гғҶгғӘгғ‘гғ©гғҒгғүгҒҢж—Ҙжң¬гҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒж–°гҒҹгҒӘжІ»зҷӮгҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
в– гғҶгғӘгғ‘гғ©гғҒгғү(Teriparatide)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гғҶгғӘгғ‘гғ©гғҒгғүгҒҜгҖҒгғ’гғҲз”ІзҠ¶и…әгғӣгғ«гғўгғі(PTH)гҒ®1пҪһ34з•Әзӣ®гҒ®гӮўгғҹгғҺй…ёгҒ«
зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгғҡгғ—гғҒгғүгҒ§гҖҒйҒәдјқеӯҗзө„гҒҝжҸӣгҒҲгҒ«гӮҲгӮҠз”Јз”ҹгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еүҜз”ІзҠ¶и…әж©ҹиғҪдәўйҖІз—ҮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЎҖдёӯPTHгҒҢжҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«й«ҳгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜгҖҒ
йӘЁеҗёеҸҺгҒҢдәўйҖІгҒ—йӘЁеҜҶеәҰгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйӘЁз•°еҢ–дҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
гҒ“гӮҢгӮ’й–“ж¬ зҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйӘЁеҪўжҲҗгҒҢдҝғйҖІгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӣёеҸҚгҒҷгӮӢ
дҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дҪңз”ЁгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒйӘЁеҪўжҲҗгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶ
ж–°гҒҹгҒӘжІ»зҷӮжі•гҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒӨгҒӨгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_058гҖ‘пҪһгҖҗIFI_062гҖ‘гҖҸ
зұіеӣҪгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒ§гҖҒйӘЁжҠҳдәҲйҳІеҠ№жһңгҒҢз«ӢиЁјгҒ•гӮҢ
2002е№ҙгҒ«зұіеӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_063гҖ‘гҖҸ
ж¬ЎгҒ„гҒ§гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒӘгҒ©гҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢ(ClinicalTrials.govжІ»йЁ“з•ӘеҸ·гҖҖNCT00433160)
гҒқгҒ®зөҗжһңжңүеҠ№жҖ§гҖҒе®үе…ЁжҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҖҒ2010е№ҙпј—жңҲгҒ«жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒ
10жңҲгӮҲгӮҠзҷәеЈІй–Ӣе§ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
(еҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢиіҮж–ҷгҖҖhttp://tinyurl.com/5sb8ztu)
зҸҫеңЁгҒ§гҒҜдё–з•ҢгҒ®86гғ¶еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
1ж—Ҙ1еӣһгҒ®зҡ®дёӢжіЁе°„гҒ«гӮҲгӮӢжҠ•дёҺгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжүҝиӘҚжҷӮгҒ«гҒҜ18гғ¶жңҲгҒҫгҒ§гӮ’
жҠ•дёҺжңҹй–“гҒ®дёҠйҷҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зҸҫеңЁгҒҜ24гғ¶жңҲгҒҫгҒ§е»¶й•·гҒ•гӮҢжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒй«ҳгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ иЎҖз—ҮгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ„гҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_061гҖ‘гҖҸ
гғ©гғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢеүҚиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒ§зҷәзҷҢжҖ§гҒҢз–‘гӮҸгӮҢгҒҹгӮҒгҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_064гҖ‘гҖҸ
й•·жңҹгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҠ•дёҺгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгғ“гӮ№гғӣгӮ№гғӣгғҚгғјгғҲгҒЁгҒ®дҪөз”ЁгҒҜеҠ№жһңгҒҢз„ЎгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_060гҖ‘гҖҸ
и…°иғҢйғЁз—ӣгҒ®зҷәз”ҹй »еәҰгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶе ұе‘ҠгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_065гҖ‘гҖҸ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжҜҺж—Ҙзҡ®дёӢжіЁе°„гӮ’иЎҢгҒҶгҒ®гҒҜжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮиІ жӢ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
жҠ•дёҺгӮ’йҖұдёҖеӣһгҒ«гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_066гҖ‘пҪһгҖҗIFI_067гҖ‘гҖҸ
гҒҫгҒҹгғ‘гғғгғҒгҒ®иІјд»ҳгҒ«гӮҲгӮӢжІ»зҷӮгӮӮи©ҰгҒҝгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_067гҖ‘гҖҸ
2006е№ҙгҒ®гҖҢйӘЁзІ—й¬Ҷз—ҮгҒ®дәҲйҳІгҒЁжІ»зҷӮгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҖҚгҒ§гҒҜгҖҒ
PTHгҒҜгҒҫгҒ иҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒ§еҠ№жһңгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳиҝ°гҒ«жӯўгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
2011е№ҙгҒ«ж”№иЁӮгҒҢдәҲе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–°зүҲгҒ§гҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®ж–°гҒҹгҒӘзҹҘиҰӢгҒҢеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҖҒ
гғ“гӮ№гғӣгӮ№гғӣгғҚгғјгғҲгҒЁдёҰгҒігҖҒ第дёҖж¬ЎйҒёжҠһи–¬гҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йӘЁзІ—й¬Ҷз—ҮгҒ®йӘЁеҪўжҲҗдҝғйҖІеүӨ гғҶгғӘгғ‘гғ©гғҒгғү