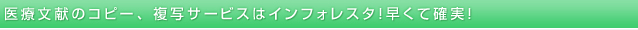=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ1гҖ‘гҒҶгҒӨз—…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮ№гғҲгғ¬гӮ№зӨҫдјҡгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒҶгҒӨз—…гҒҜгҒҫгӮҢгҒӘз–ҫжӮЈгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з”ҹж¶Ҝжңүз—…зҺҮгҒҜй«ҳгҒҸгҖҒж—Ҙжң¬гӮ„зұіеӣҪгҒ®иӘҝжҹ»гҒ§гӮӮдәәеҸЈгҒ®14пҪһ17пј…гҒ«еҸҠгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®иӘҝжҹ»гҒ§гҒҜе°‘гҒ—е°‘гҒӘгҒҸгҖҒз”·жҖ§гҒ§3.84%гҖҒеҘіжҖ§гҒ§8.44%гҖҒ
еҗҲиЁҲгҒ§6.16%гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҘіжҖ§гҒ«еӨҡгҒ„гҒ®гӮӮзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®жІ»зҷӮгӮӮи–¬зү©гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢдёӯеҝғгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ«з”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈгҒ®ж”№е–„гҒӘгҒ©гҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
и–¬еүӨгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ第дёҖдё–д»ЈгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢдёүз’°зі»гҖҒ第дәҢдё–д»ЈгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢеӣӣз’°зі»и–¬еүӨгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒ
第дёүдё–д»ЈгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢSSRIпјҲSelective Serotonin Reuptake Inhibitorпјҡ
гӮ»гғӯгғҲгғӢгғіеҶҚеҸ–гӮҠиҫјгҒҝйҳ»е®іеүӨпјүгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҖҒжІ»зҷӮгҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_083гҖ‘пҪһгҖҗIFI_085гҖ‘гҖҸ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ2гҖ‘гӮЁгӮ№гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғ©гғ пјҲEscitalopramпјү
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒҜзҘһзөҢдјқйҒ”зү©иіӘгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гғўгғҺгӮўгғҹгғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзү©иіӘгҒ®дёҖзЁ®йЎһгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гӮ·гғҠгғ—гӮ№гҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢеҸҚеҜҫеҒҙгҒ®гӮ»гғӯгғҲгғӢгғіеҸ—е®№дҪ“гҒ«дҪңз”ЁгҒ—жҙ»жҖ§гҒҢдҝқгҒҹгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғўгғҺгӮўгғҹгғігӮ’жҙ»жҖ§еҢ–гҒ•гҒӣгӮӢдёүз’°зі»жҠ—гҒҶгҒӨеүӨгҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ
гҒҶгҒӨз—…гҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒ—гҒҰгғўгғҺгӮўгғҹгғід»®иӘ¬гҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
дёӯгҒ§гӮӮгӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒҢйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒҜгӮ·гғҠгғ—гӮ№гҒ®иЈҸеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢгғҲгғ©гғігӮ№гғқгғјгӮҝгҒ§еҶҚеҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҒ•гӮҢгҖҒ
еҶҚеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒ®йҮҸгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢжҠ‘гҒҶгҒӨзҠ¶ж…ӢгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ
гӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒ®еҶҚеҸ–гӮҠиҫјгҒҝгӮ’йҳ»е®ігҒ—гҖҒгӮ»гғӯгғҲгғӢгғіжҝғеәҰгӮ’дёҠжҳҮгҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢ
SSRIгҒ®и–¬зҗҶдҪңз”ЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮӮгҒ„гҒҸзЁ®йЎһгҒӢгҒ®SSRIгҒҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮЁгӮ№гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғ©гғ гҒҜгҖҒ
дёӯгҒ§гӮӮжңҖгӮӮйҒёжҠһзҡ„гҒӘйҳ»е®ідҪңз”ЁгҒҢеј·гҒҸгҖҒеҠ№жһңгҒ®зҷәзҸҫгҒҢж—©гҒ„гҖҒйҮҚз—ҮгҒ«гӮӮжңүеҠ№гҒӘгҒ©гҒ®
зү№еҫҙгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғ©гғ пјҲCitalopramпјүгҒ®е…үеӯҰз•°жҖ§дҪ“пјҲSдҪ“пјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
жҠ—гҒҶгҒӨеҠ№жһңгҒҜгҒ“гҒ®SдҪ“гҒ®гҒҝгҒҢжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®з•°жҖ§дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢRдҪ“гҒҜгҖҒгӮ»гғӯгғҲгғӢгғігҒ®гғҲгғ©гғігӮ№гғқгғјгӮҝгҒ§гҒ®
еҶҚеҸ–гӮҠиҫјгҒҝйҳ»е®ігӮ’е№ІжёүгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гҒ®RдҪ“гӮ’йҷӨгҒ„гҒҹгӮЁгӮ№гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғӯгғ гҒҜ
гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғӯгғ гӮҲгӮҠгӮӮеҠӣдҫЎгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒзҙ„2еҖҚгҒ®еҶҚеҸ–гӮҠиҫјгҒҝйҳ»е®ідҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_086гҖ‘гҖҸ
2001е№ҙгҒ«гӮ№гӮЁгғјгғҮгғігҒ§гҖҒ2002е№ҙгҒ«гҒҜ欧зұігҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘжқҘгҖҒ
дё–з•ҢгҒ®96гғ¶еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2011е№ҙ4жңҲгҒ«жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§ж¬§зұігҒ§гҒҜж•°еӨҡгҒҸгҒ®иҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжүҝиӘҚгҒёиҮігӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгҒ®иҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е°ҸиҰҸжЁЎгҒӘе®үе…ЁжҖ§и©ҰйЁ“гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_087гҖ‘гҖҸгҖҒ
з”ЁйҮҸгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дёӯиҰҸжЁЎгҒӘи©ҰйЁ“гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_088гҖ‘гҖҸгҖҒ
paroxetineгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйқһеҠЈжҖ§и©ҰйЁ“гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_089гҖ‘гҖҸгҖҒ
й•·жңҹжҠ•дёҺи©ҰйЁ“гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_090гҖ‘гҖҸгҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе®үе…ЁжҖ§гҒЁжңүеҠ№жҖ§гҖҒжҠ•дёҺйҮҸпјҲ20mgпјүгҒӘгҒ©гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮігӮҜгғ©гғігғ¬гғ“гғҘгғјгҒ§гӮӮcitalopramгҒӘгҒ©гҒ®д»–еүӨгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰеҗҢж§ҳгҒ®зөҗжһңгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
PubMedгҒ§иӢұж–ҮжҠ„йҢІгҒҢиӘӯгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
http://1.usa.gov/pVGu0v
гҒҶгҒӨз—…гҒ®жҢҒгҒӨеҒҙйқўгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢе…ЁиҲ¬зҡ„дёҚе®үйҡңе®і(Generalized anxiety disorder:GAD)
гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒSSRIгҒҜжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_091гҖ‘гҖҗIFI_092гҖ‘гҖҸ
дёӯгҒ§гӮӮEscitalopramгҒ§гҒҜжҖҘжҖ§жңҹеҲқжңҹжІ»зҷӮгӮ„еҶҚзҷәдәҲйҳІгҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_084гҖ‘гҖҗIFI_093гҖ‘гҖҸ
第дёүдё–д»ЈжҠ—гҒҶгҒӨеүӨгҖҖгӮЁгӮ№гӮ·гӮҝгғӯгғ—гғ©гғ