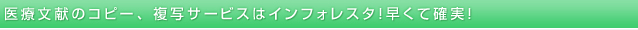й–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒҜй–ўзҜҖж»‘иҶңгҒ®ж…ўжҖ§зҡ„гҒӘзӮҺз—ҮгҒ§гҖҒ
й–ўзҜҖи»ҹйӘЁгӮ„йӘЁгҒ®з ҙеЈҠгҒҢжҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«йҖІиЎҢгҒҷгӮӢз–ҫжӮЈгҒ§гҒҷгҖӮ
з—…еӣ гҒҜгҒҫгҒ жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҜгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒе…Қз–«жҖ§з•°еёёгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁ
иҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
30жүҚпҪһ50жүҚгҒ®еҘіжҖ§гҒ«еӨҡгҒҸзҷәз—…гҒ—гҖҒжңүз—…зҺҮгҒҜдәәеҸЈгҒ®0.4пҪһ0.5пј…гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁ
гҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҒҠгӮҲгҒқ70дёҮдәәгҒ®жӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жІ»зҷӮжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҒҜйқһгӮ№гғҶгғӯгӮӨгғүжҠ—зӮҺз—Үи–¬пјҲNSAIDsпјүгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
е…Қз–«еҲ¶еҫЎгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹжҠ—гғӘгӮҰгғһгғҒи–¬гғЎгӮҪгғҲгғ¬гӮӯгӮ»гғјгғҲпјҲMTXпјүгҒҢ
жЁҷжә–зҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒй–ўзҜҖз ҙеЈҠгӮ’йҳІгҒҺгҒҚгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ
ж–°гҒҹгҒ«TNFпјҲTumor necrosis factorпјүйҳ»е®іи–¬гҒҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҖҒ
ж–°гҒҹгҒӘжІ»зҷӮгҒ®ж–№еҗ‘гҒҢй–ӢжӢ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_108гҖ‘гҖҸ
ж—Ҙжң¬гғӘгӮҰгғһгғҒеӯҰдјҡгҒ®
гҖҢй–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒпјҲRAпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢTNFйҳ»е®ізҷӮжі•ж–ҪиЎҢгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҖҚгҒ§гҒҜ
гҖҢж—ўеӯҳгҒ®жҠ—гғӘгӮҰгғһгғҒи–¬йҖҡеёёйҮҸгӮ’3гғ¶жңҲд»ҘдёҠз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгӮӮ
гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«дёҚиүҜгҒ®RAжӮЈиҖ…гҖҚгҒ«гҒҜTNFйҳ»е®іи–¬гҒ®дҪҝз”ЁгҒҢжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_109гҖ‘гҖҸ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹдёӯгҒ§й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹи–¬еүӨгҒҢгӮӨгғігғ•гғӘгӮӯгӮ·гғһгғ–(Infliximab)гҖҒ
гӮўгғҖгғӘгғ–гғһгғ–(Adalimumab)гҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжңҖж–°гҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰ
гӮҙгғӘгғ гғһгғ–гҒҢжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗпј‘гҖ‘гӮҙгғӘгғ гғһгғ–(Golimumab)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮҙгғӘгғ гғһгғ–гҒҜгғҲгғ©гғігӮ№гӮёгӮ§гғӢгғғгӮҜгғһгӮҰгӮ№гҒ§дҪңгӮӢIgGгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гғ’гғҲгҒ®гӮҝгғігғ‘гӮҜиіӘгҒ®гҒҝгӮ’жңүгҒҷгӮӢе®Ңе…Ёгғ’гғҲеһӢгҒ®жҠ—TNF-ОұжҠ—дҪ“
пјҲзӮҺз—ҮжҖ§гӮөгӮӨгғҲгӮ«гӮӨгғігҒ®дёҖзЁ®пјүгҒ§гҒҷгҖӮ
е…ҲиЎҢгҒҷгӮӢеҗҢж§ҳгҒ®з”ҹзү©иЈҪеүӨгҒ§гҒӮгӮӢгӮӨгғігғ•гғӘгӮӯгӮ·гғһгғ–гҒӘгҒ©гҒҢгӮӯгғЎгғ©еһӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
жҠ•дёҺжҷӮгҒ®еҚіеҠ№жҖ§гӮ„еҠ№жһңгҒҢжёӣиЎ°гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®ж¬ зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
е®Ңе…Ёгғ’гғҲеһӢгҒ®гӮҙгғӘгғ гғһгғ–гҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зӮ№гӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹзү©иЈҪеүӨгҒҜй–ўзҜҖз ҙеЈҠгӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢеҠ№жһңгӮӮиҰӢгӮүгӮҢгҖҒй–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒ®жІ»зҷӮж–№йҮқгҒҢ
й–ўзҜҖз—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгҒӢгӮүгҖҒй–ўзҜҖз ҙеЈҠйҳ»жӯўгҒёгҒЁеҗ‘гҒӢгҒ„гҖҒе®Ңе…ЁеҜӣи§ЈгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮ
гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_110гҖ‘пҪһгҖҗIFI_111гҖ‘гҖҸ
2005е№ҙгӮҲгӮҠGO-FORWARDи©ҰйЁ“пјҲ第3зӣёи©ҰйЁ“гҖҖClinicalTrials.govгҒ®
иҮЁеәҠи©ҰйЁ“з•ӘеҸ·гҖҖNCT00264550пјүгҒӘгҒ©еӨҡгҒҸгҒ®иҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒ
MTXгҒ«гӮҲгӮӢжІ»зҷӮгҒҢдёҚиүҜгҒ®е ҙеҗҲгҖҒMTXгҒЁгҒ®дҪөз”ЁгҒ§гҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒЁе®үе…ЁжҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_112гҖ‘пҪһгҖҗIFI_116гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®и©ҰйЁ“гҒ§гҒҜд»–гҒ®з”ҹзү©и–¬еүӨгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ®е„ӘдҪҚжҖ§гҒҜзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
4йҖұгҒ«1еӣһгҒ®зҡ®дёӢжіЁе°„гҒ§еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ
жӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ®QOLгҒ«еҸҠгҒјгҒҷеҪұйҹҝгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҖҒеӨ§еӨүдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„и–¬еүӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮ第3зӣёгҒ®и©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒ еӯҰдјҡзҷәиЎЁгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒ
дёҠиЁҳгҒ®и©ҰйЁ“зөҗжһңгӮ’иҝҪиӘҚгҒҷгӮӢзөҗжһңгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_117гҖ‘пҪһгҖҗIFI_118гҖ‘гҖҸ
Cochrane LibraryгҒ«гҒҜгӮ·гӮ№гғҶгғһгғҶгӮЈгғғгӮҜгғ¬гғ“гғҘгғјгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
J RheumatolиӘҢгҒ«гҒҜи«–ж–ҮгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_119гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®зөҗжһңгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒ2009е№ҙ7жңҲгҒ«гҒҜзұігҖҒеҠ гҖҒ欧е·һгҒӘгҒ©гҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒ
дё–з•ҢгҒ®40гғ¶еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
2011е№ҙ7жңҲгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲеҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢжүҝиӘҚжғ…е ұгҖҖhttp://bit.ly/netQZAпјү
9жңҲ12ж—ҘгҒ«гҒҜгҖҒд»–гҒ®17и–¬еүӨгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«и–¬дҫЎеҸҺијүгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮҙгғӘгғ гғһгғ–гҒҜ4йҖұгҒ«1еәҰгҒ®зҡ®дёӢжіЁе°„гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гҒ•гӮүгҒ«12йҖұгҒ§пј‘еәҰгҒ®йқҷи„ҲжіЁе°„гҒ«гӮҲгӮӢеҠ№жһңгӮ’иҰӢгӮӢGO-LIVEи©ҰйЁ“гӮӮйҖІиЎҢдёӯгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_120гҖ‘гҖҸ
й–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒ®з”ҹе‘ҪдәҲеҫҢгҒҜеҒҘеёёдәәгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰзҙ„10е№ҙжӮӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
TNFйҳ»е®іи–¬гҒҢз”ҹе‘ҪдәҲеҫҢгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_121гҖ‘гҖҸ
й–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒ®ж–°гҒ—гҒ„TNFйҳ»е®іи–¬гҖҖгӮҙгғӘгғ гғһгғ–