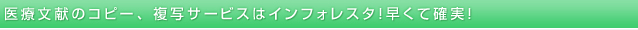еӨҡзҷәжҖ§йӘЁй«„и…«гҒҜгҖҒе…Қз–«гӮ°гғӯгғ–гғӘгғігӮ’з”Јз”ҹгҒҷгӮӢеҪўиіӘзҙ°иғһгҒҢи…«зҳҚеҢ–гҒ—
еў—ж®–гҒҷгӮӢиЎҖж¶ІгҒҢгӮ“гҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒҷгҖӮ
CRABз—ҮеҖҷгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢй«ҳгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ иЎҖз—ҮгҖҒи…ҺдёҚе…ЁгҖҒиІ§иЎҖгҖҒйӘЁжҗҚеӮ·гҒӘгҒ©гӮ’
дё»гҒҹгӮӢз—ҮзҠ¶гҒЁгҒ—гҒҹеӨҡж§ҳгҒӘз—ҮзҠ¶гӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҪ№жӮЈзҺҮгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ10дёҮдәәгҒӮгҒҹгӮҠ3.5дәә/е№ҙгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ欧зұігӮҲгӮҠгҒҜ
е°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒ«еӨҡгҒҸгҖҒз”·жҖ§гӮҲгӮҠгҒҜеҘіжҖ§гҒҢгӮ„гӮ„еӨҡгҒ„гҒ®гӮӮзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_094гҖ‘гҖҸ
иҝ‘е№ҙгҖҒгӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгӮ’е§ӢгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®жІ»зҷӮи–¬гҒҢж—Ҙжң¬гҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒ
ж–°гҒҹгҒӘжІ»зҷӮжі•гҒ®еұ•й–ӢгҒЁгҒ—гҒҰжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_095гҖ‘гҖҸ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гҖҗ1гҖ‘гӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүпјҲThalidomideпјү
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒ®и–¬зҗҶдҪңз”ЁгҒҜгҖҒжңӘгҒ е®Ңе…ЁгҒ«гҒҜи§ЈжҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒ
йӘЁй«„и…«зҙ°иғһгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘгӮўгғқгғҲгғјгӮ·гӮ№иӘҳе°ҺгӮ„гҖҒ
йӘЁй«„й–“иіӘзҙ°иғһдёҠгҒ®жҺҘзқҖеӣ еӯҗгҒ®дҪҺдёӢгҒ«гӮҲгӮӢйӘЁй«„и…«зҳҚзҙ°иғһгҒЁгҒ®зӣёдә’дҪңз”ЁгҒ®жҠ‘еҲ¶гҖҒ
VEGFгӮ„TNF-ОұгҒӘгҒ©гҒ®еҗ„зЁ®гӮөгӮӨгғҲгӮ«гӮӨгғігҒ®жҠ‘еҲ¶гҖҒTзҙ°иғһгғ»NKзҙ°иғһгҒёгҒ®
дҪңз”ЁгҒ«гӮҲгӮӢжҠ—йӘЁй«„и…«е…Қз–«гҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гҒӘгҒ©гҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҒқгӮҢгӮүгҒ«гӮҲгӮӢиЎҖз®Ўж–°з”ҹгҒ®жҠ‘еҲ¶дҪңз”ЁгӮӮзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_096гҖ‘пҪһгҖҗIFI_098гҖ‘гҖҸ
гӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒҜгҖҒ1957е№ҙгҒ«йҺ®йқҷгғ»зқЎзң и–¬гҒЁгҒ—гҒҰзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
1960е№ҙд»ЈеҲқй ӯгҒ«гҖҒеӮ¬еҘҮеҪўжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮеҚғдәәгҒ«еҸҠгҒ¶
жӮЈиҖ…гҒҢеҮәгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдёҚе№ёгҒӘи»ўеё°гӮ’иҝҺгҒҲзҷәеЈІгҒҢдёӯжӯўгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒ1994е№ҙгҒ«иЎҖз®Ўж–°з”ҹжҠ‘еҲ¶дҪңз”ЁгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒ
зҷҢгҒ®жІ»зҷӮи–¬гҒЁгҒ—гҒҰеҶҚзҷ»е ҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
1999е№ҙгҒ«гҒҜеҶҚзҷәгғ»йӣЈжІ»жҖ§гҒ®еӨҡзҷәжҖ§йӘЁй«„и…«жІ»зҷӮи–¬гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_099гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгҒ«е…Ҳз«ӢгҒӨ1997е№ҙгҒ«гӮўгғјгӮ«гғігӮҪгғје·һз«ӢеӨ§еӯҰгҒ«е…ҘйҷўжІ»зҷӮдёӯгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹжӮЈиҖ…гҒ®еҰ»гҒҢгҖҒ
иҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒ§ж–ҮзҢ®гӮ’иӘҝгҒ№гҖҒгӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒ®жҠ—и…«зҳҚеҠ№жһңгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҖҒ
жӢ…еҪ“еҢ»гҒ«гҒқгҒ®дҪҝз”ЁгӮ’з”ігҒ—еҮәгҒҹгҒ®гҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶйҖёи©ұгӮӮж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_100гҖ‘гҖҸ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮ2008е№ҙ10жңҲгҒ«гҖҒеҶҚзҷәгҒҫгҒҹгҒҜйӣЈжІ»жҖ§йӘЁй«„и…«жІ»зҷӮи–¬гҒЁгҒ—гҒҰ
жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
欧зұігҒ§гҒҜеҲқжңҹжІ»зҷӮи–¬гҒЁгҒ—гҒҰжЁҷжә–зҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜеҶҚзҷәеҫҢгҒ®дәҲеҫҢгҒҢзҹӯгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®зҗҶз”ұгҒӢгӮүгҖҒгҒҫгҒ еҲқжңҹжІ»зҷӮгҒ§гҒҜдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒ移жӨҚеҫҢгҒ®з¶ӯжҢҒзҷӮжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҠ№жһңгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_101гҖ‘гҖҸ
зү№гҒ«ең°еӣәгӮҒзҷӮжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғңгғ«гғҶгӮҫгғҹгғ–гҒЁгҒ®дҪөз”ЁзҷӮжі•гҒҢ
еҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_102гҖ‘пҪһгҖҗIFI_104гҖ‘гҖҸ
гӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒ®жҢҒгҒӨеӮ¬еҘҮеҪўжҖ§гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҖҒ
гҒқгҒ®дҪҝз”ЁгҒ«гҒҜзҙ°еҝғгҒ®жіЁж„ҸгҒҢгҒҜгӮүгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
TERMS(thalidomide education and risk management system)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢ
з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҖҒиғҺе…җгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒ®жҡҙйңІгӮ’йҳІгҒҗеҠӘеҠӣгҒҢ
гҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгӮ’дҪҝз”ЁеҮәжқҘгӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ
ж—Ҙжң¬иЎҖж¶ІеӯҰдјҡз ”дҝ®ж–ҪиЁӯгҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–ҪиЁӯгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
дҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»её«гӮӮжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_105гҖ‘пҪһгҖҗIFI_106гҖ‘гҖҸ
еӨҡзҷәжҖ§йӘЁй«„и…«гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§жІ»зҷ’еӣ°йӣЈгҒӘйҖ иЎҖеҷЁи…«зҳҚгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
ж–°иҰҸи–¬еүӨгҒ®дҪҝз”ЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе®Ңе…ЁеҜӣи§ЈгҒёгҒ®йҒ“гҒҢй–ӢгҒ‘гҖҒ
жІ»зҷ’гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢжІ»зҷӮгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_102гҖ‘гҖҗIFI_107гҖ‘гҖҸ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒзҸҫзҠ¶гҒ§гҒҜгҒҫгҒ з”ҹеӯҳжңҹй–“гҒ®е»¶й•·гҒҢеҪ“йқўгҒ®зӣ®жЁҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҲҶеӯҗгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®зҷәз—ҮгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮӮи§ЈжҳҺгҒ•гӮҢгҒӨгҒӨгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒ
гҒ©гҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжІ»зҷӮгӮ’иЎҢгҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮ
次第гҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨҡзҷәжҖ§йӘЁй«„и…«гҒ®гӮөгғӘгғүгғһгӮӨгғүгҒ«гӮҲгӮӢжІ»зҷӮ