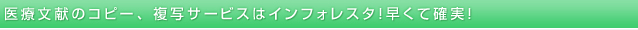糖尿病の合併症の一つである網膜症による失明は、
年間3000人にもおよび、社会的にも大きな損失であるばかりではなく、
患者さんの生活に及ぼす影響も小さくありません。
糖尿病性網膜症による失明は、緑内障によるものに次いで2番目に多く、
特に就労年代での中途失明の主要な原因となっています。
病態としては、血管透過性亢進のみ見られる単純網膜症から、
網膜血管に閉塞の見られる前増殖網膜症、さらに血管新生の見られる
増殖性網膜症へと進行します。
それらの全てのステージで黄斑浮腫が見られると視力が低下し、
失明に繋がります。
治療法としては、内科的にはステロイド剤によるもの、外科的には光凝固、
硝子体手術などが行われてきましたが、硝子体などにVEGF
(Vascular endotherial growth factor:血管内皮細胞増殖因子)が
多く見られることから抗VEGF抗体の効果が知られるようになり、
ベバシズマブなどが併用されるようになってきました。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
【1】ベバシズマブ(Bevacizumab)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ベバシズマブはVEGFに対するマウスモノクローナル抗体を
遺伝子組み換え技術によりヒト化した中和抗体で、VEGFと特異的に結合し
血管新生を阻害する作用を持っています。
硝子体内へ注入することで前房内のVEGF濃度を低下させ、
血管新生の退縮と血管透過性亢進の抑制を行います。
『参考文献:【IFI_122】』
2006年にSpaideが初めて増殖糖尿病網膜症に対する
ベバシズマブ硝子体内注射により1週間以内に視力が改善し、
1ヶ月で新生血管が退縮したと報告しました。
『参考文献:【IFI_123】』
ただ、ベバシズマブ単独での効果は、作用期間が短く1~2週間程度であるため、
繰り返し投与する必要があることが指摘されています。
『参考文献:【IFI_124】~【IFI_126】』
薬剤としては即効性があるため
『参考文献:【IFI_127】~【IFI_128】』
手術療法の術前薬として注目されました。
具体的には、活動性の高い血管増殖や新生血管が見られる場合に、
手術前にベバシズマブを硝子体内に注射することにより、
術中の出血が軽減されるため、手術がしやすくなるというものです。
『参考文献:【IFI_125】【IFI_129】~【IFI_130】』
症例報告もいくつか出ています。
『参考文献:【IFI_131】~【IFI_134】』
またメタアナリシスが行われており、短期的な効果については
エビデンスがあるとされています。
『参考文献:【IFI_135】』
白内障手術後における糖尿病黄斑浮腫に対してベバシズマブを
硝子体内へ注入することも、網膜厚を減少させ、視力低下や失明のリスクを
下げる効果があるとの報告もあります。
『参考文献:【IFI_136】』
しかしながら、現状ではベバシズマブは糖尿病網膜症治療薬としては、
日本でも欧米でも承認されている訳ではありません。
日本では2007年に「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」の
治療薬として承認されているのみです。
ただ、上記のような抗VEGF効果が認められており、
抗癌剤として承認されていることから入手がしやすい、
また比較的安価であるなどの理由から、保険適用外ではありますが、
臨床的には重要な薬剤と考えることができます。
糖尿病網膜症の治療においては、まず糖尿病の治療が基本ですが、
同時に合併症の治療も大切であり、
ベバシズマブには大きな期待が寄せられています。
糖尿病眼合併症に対する血管新生阻害剤 ベバシズマブ