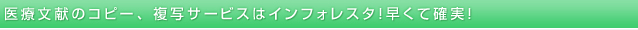гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“гҒ®жңүз—…зҺҮгҒҜ0.5пҪһ1%зЁӢеәҰгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒ
дё–з•ҢгҒ§5000дёҮдәәгҖҒж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§гӮӮ100дёҮдәәгҒ®жӮЈиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з—…ж…ӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҢеұҖжүҖжҖ§гҒӘгҒ„гҒ—е…ЁиҲ¬жҖ§гҒ®йҒҺеҗҢжңҹпјҲйҒҺеү°пјүзҘһзөҢзҷәе°„гҒ«гӮҲгӮӢ
дёӯжһўзҘһзөҢж©ҹиғҪгҒ®зҷәдҪңзҡ„гҒӘж’№д№ұзҸҫиұЎгӮ’дё»з—ҮзҠ¶гҒЁгҒҷгӮӢз—ҮеҖҷзҫӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚ
гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_150гҖ‘гҖҸ
жІ»зҷӮж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜи–¬зү©жІ»зҷӮгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“20е№ҙгҒҸгӮүгҒ„гҒ®й–“гҒ«гҖҒж–°гҒҹгҒӘи–¬зҗҶдҪңз”ЁгӮ’жҢҒгҒӨж–°иҰҸжҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҒҢ
ж¬ЎгҖ…гҒЁй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжүҝиӘҚгҒҢгҒҷгҒҷгӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҖҒиҮЁеәҠгҒ«гӮӮйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
в—Ҷ гғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ пјҲLevetiracetamпјү
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
гғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒҜе…үеӯҰжҙ»жҖ§гӮ’гӮӮгҒӨгғ”гғӯгғӘгғүгғіиӘҳе°ҺдҪ“пјҲS-е…үеӯҰз•°жҖ§дҪ“пјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
зҘһзөҢзөӮжң«гҒ®гӮ·гғҠгғ—гӮ№е°Ҹиғһ2AпјҲSV2AпјүгҒЁзү№з•°зҡ„гҒ«зөҗеҗҲгҒ—зҘһзөҢдјқйҒ”гӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢ
еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_151гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®жҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҒҢзҘһзөҢзҙ°иғһгҒҠгӮҲгҒізҘһзөҢдјқйҒ”зі»гҒ®йҒҺеү°гҒӘиҲҲеҘ®гӮ’
жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйӣ»дҪҚдҫқеӯҳжҖ§гӮӨгӮӘгғіпјҲNa+гӮ„Ca+пјүгғҒгғЈгғігғҚгғ«гӮ’йҳ»е®ігҒ—гҒҹгӮҠгҖҒ
GABAдҪңеӢ•жҖ§зҘһзөҢгҒ®еў—еј·гҖҒгӮ°гғ«гӮҝгғҹгғій…ёдҪңеӢ•жҖ§зҘһзөҢжҠ‘еҲ¶гҒӘгҒ©гӮ’дё»гҒӘи–¬зҗҶдҪңз”ЁгҒЁ
гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҒд»–гҒ®и–¬еүӨгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘи–¬зҗҶдҪңз”ЁгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒ®
еӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»–еүӨгҒЁгҒ®дҪөз”ЁзҷӮжі•гӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҒ®дҪөз”ЁгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒдҪңз”ЁгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ®з•°гҒӘгӮӢи–¬еүӨгӮ’
йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҺҹеүҮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_152гҖ‘гҖҸ
гҒ•гӮүгҒ«гғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒҜгҖҒзөҢеҸЈжҠ•дёҺеҫҢгҒҷгҒҝгӮ„гҒӢгҒ«ж¶ҲеҢ–з®ЎгӮҲгӮҠеҗёеҸҺгҒ•гӮҢгҖҒ
жҠ•дёҺеҫҢ1жҷӮй–“гҒ§иЎҖдёӯжҝғеәҰгҒҢгғ”гғјгӮҜгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҚҠжёӣжңҹгҒҜжҲҗдәәгҒ§6пҪһ8жҷӮй–“гҒӘгҒ®гҒ§
1ж—Ҙ2еӣһжҠ•дёҺгҒ§48жҷӮй–“еҫҢгҒ«гҒҜе®ҡеёёзҠ¶ж…ӢгҒ«йҒ”гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҠ гҒҲгҒҰиӮқиҮ“гҒ§гҒ®д»Ји¬қй…өзҙ гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҡгҖҒи…ҺиҮ“гӮҲгӮҠжҺ’жі„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒ
и–¬зү©зӣёдә’дҪңз”ЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒҸгҖҒд»–еүӨгҒЁгҒ®дҪөз”ЁгҒҢе®№жҳ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_153гҖ‘гҖҸ
QOLгҒҢдёҠжҳҮгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_154гҖ‘гҖҸ
жө·еӨ–гҒ§ж§ҳгҖ…гҒӘиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹзөҗжһңгҖҒ1999е№ҙгҒ«зұіеӣҪгҒ§гҖҒ
2000е№ҙгҒ«ж¬§е·һгҒ§зҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘжқҘгҖҒдё–з•ҢгҒ®92гғ¶еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгғ»иІ©еЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§гӮӮиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒ213дҫӢгҒ®йӣЈжІ»йғЁеҲҶгҒҰгӮ“гҒӢгӮ“гҒ§гҒ®гғ—
гғ©гӮ»гғңеҜҫз…§и©ҰйЁ“гҒ§зҷәдҪңжёӣе°‘зҺҮгҖҒ50%гғ¬гӮ№гғқгғігғҖгғјгғ¬гғјгғҲгҖҒ
зҷәдҪңж¶ҲеӨұзҺҮгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒ§гӮӮеҜҫз…§зҫӨгҒ«еҜҫгҒ—жңүж„ҸгҒӘзөҗжһңгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_155гҖ‘гҖҸ
2008е№ҙгҒ«ж—Ҙжң¬е°Ҹе…җзҘһзөҢеӯҰдјҡгӮҲгӮҠж—©жңҹжүҝиӘҚгҒ®иҰҒжңӣжӣёгҒҢеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ«
жҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2010е№ҙ7жңҲгҒ«жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҢд»–гҒ®жҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘеҠ№жһңгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“жӮЈиҖ…гҒ®йғЁеҲҶзҷәдҪң
пјҲдәҢж¬ЎжҖ§е…ЁиҲ¬еҢ–зҷәдҪңгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҒЁгҒ®дҪөз”ЁзҷӮжі•гҖҚгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҖҒ
9жңҲгҒ«гҒҜзҷәеЈІгҒҢй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲеҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮеҷЁж©ҹз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢгҖҖжүҝиӘҚжғ…е ұгҖҖhttp://bit.ly/uDhI71пјү
зұіеӣҪгҒ®гӮЁгӮӯгӮ№гғ‘гғјгғҲгӮӘгғ”гғӢгӮӘгғі2005гҒ§гӮӮгҖҒгғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒҜз—ҮеҖҷжҖ§йғЁеҲҶ
гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“гҒ§гӮ«гғ«гғҗгғһгӮјгғ”гғігҒӘгҒ©гҒЁгҒ®дҪөз”ЁзҷӮжі•гҒ§з¬¬дёҖйҒёжҠһи–¬гҒ«гҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_156гҖ‘гҖҸвҖ»гҒ“гҒЎгӮүгҒ®ж–ҮзҢ®гҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®жҰӮиҰҒгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҸҫеңЁгҒҜдҪөз”ЁзҷӮжі•гҒ®гҒҝгҒ®жүҝиӘҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖж¬ЎйҒёжҠһи–¬гҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮ
зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_157гҖ‘гҖҸ
гҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“еӯҰдјҡгҒҜ2011е№ҙ6жңҲгҒ«
гҖҢгҒҰгӮ“гҒӢгӮ“гҒ®и–¬зү©зҷӮжі•гҒҜгҖҒеӨҡеүӨдҪөз”ЁгӮҲгӮҠеҚҳеүӨжҠ•дёҺгҒ®ж–№гҒҢи–¬зү©зӣёдә’дҪңз”ЁгҒ«гӮҲгӮӢ
е®үе…ЁжҖ§гҒ®зӮ№гҒӢгӮүжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁгҒ®иҰҒжңӣжӣёгӮ’еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒёжҸҗеҮәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
гғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒ®еҚҳеүӨжҠ•дёҺгҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮӮзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
欧зұігҒ§гҒҜгҖҒ4жүҚд»ҘдёҠгҒ®е°Ҹе…җгҒ§гӮӮдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮе°Ҹе…җгҒёгҒ®жҠ•дёҺгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_158гҖ‘пҪһгҖҗIFI_159гҖ‘гҖҸ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒеҰҠе©ҰгӮ„жҺҲд№ідёӯгҒ®еҘіжҖ§гҒёгҒ®жҠ•и–¬гҒ«гҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ®иҰӢи§ЈгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_160гҖ‘гҖҸ
еҮәз”ҹз•°еёёгӮ’жқҘгҒ•гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғҮгғігғһгғјгӮҜгҒ§гҒ®з ”究зөҗжһңгӮӮжңҖиҝ‘зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_161гҖ‘гҖҸ
еүҜдҪңз”ЁгҒ®жҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒ„гғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ гҒ®иҮЁеәҠеҝңз”ЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°иҰҸжҠ—гҒҰгӮ“гҒӢгӮ“и–¬гҖҖгғ¬гғҷгғҒгғ©гӮ»гӮҝгғ