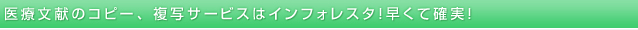и…Һзҙ°иғһзҷҢгҒҜгҖҒе°ҝзҙ°з®Ўзҙ°иғһз”ұжқҘгҒ§гҖҒ
и…ҺиҮ“гӮ’еҺҹзҷәгҒЁгҒҷгӮӢи…«зҳҚгҒ®85-90%гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жӮЈиҖ…ж•°гҒҜе№ҙгҖ…еў—еҠ гҒ®еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒ2002е№ҙгҒ®и…ҺзҷҢз ”з©¶дјҡгҒ®иӘҝжҹ»гҒ§гҒҜгҖҒ
жӮЈиҖ…ж•°гҒҢе…ЁеӣҪгҒ§7437дәәгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ転移жҖ§гҒ®зҷҢгҒ§гҒҜзү№гҒ«дәҲеҫҢгҒҢжӮӘгҒҸгҖҒ
5е№ҙз”ҹеӯҳзҺҮгҒҜ20%еүҚеҫҢгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲқжңҹгҒ®ж®өйҡҺгҒ§зҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜжүӢиЎ“гҒ«гӮҲгӮӢж‘ҳеҮәгҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гҒқгҒ®еҫҢеҶҚзҷәгӮ„転移гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒи–¬зү©зҷӮжі•гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
第дёҖйҒёжҠһи–¬гҒҜгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғігҒӘгҒ©гҒ®гӮөгӮӨгғҲгӮ«гӮӨгғігҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҘҸеҠҹзҺҮгҒҢжӮӘгҒҸгҖҒ
гҒқгҒ®еҫҢгҒ«гҒҜгӮ№гғӢгғҒгғӢгғ–гӮ„гӮҪгғ©гғ•гӮ§гғӢгғ–гҒӘгҒ©гҖҒжңҖиҝ‘ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮжүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹ
гғҒгғӯгӮ·гғігӮӯгғҠгғјгӮјйҳ»е®іи–¬гҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дәҢж¬Ўи–¬еүӨгӮӮиҖҗжҖ§гҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒ
пҪҚTORпјҲMammalian Target of rapamycinпјүйҳ»е®іи–¬гҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
-------------------------------
в—Ҷ гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№пјҲEverolimusпјү
-------------------------------
гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒҜгғ©гғ‘гғһгӮӨгӮ·гғігҒ®иӘҳе°ҺдҪ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гғ©гғ‘гғһгӮӨгӮ·гғігҒҜгӮӨгғјгӮ№гӮҝгғјеі¶гҒ®еңҹеЈҢгҒӢгӮүзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹж”ҫз·ҡиҸҢгҒҢз”Јз”ҹгҒҷгӮӢ
гғһгӮҜгғӯгғ©гӮӨгғүзі»жҠ—з”ҹзү©иіӘгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖеҲқгҒҜжҠ—зңҹиҸҢи–¬гҒЁгҒ—гҒҰз ”з©¶гҒ•гӮҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒгӮҝгӮҜгғӯгғӘгғ гӮ№гҒЁж§ӢйҖ гҒҢдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе…Қз–«жҠ‘еҲ¶еүӨгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®
з ”з©¶гҒҢйҖІгҒҝгҖҒиҮ“еҷЁз§»жӨҚеҫҢгҒ®е…Қз–«жҠ‘еҲ¶еүӨгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_184гҖ‘пҪһгҖҗIFI_185гҖ‘гҖҸ
гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒҜmTORгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒҷгҖӮ
mTORгҒҜзҷҢзҙ°иғһгҒ®еў—ж®–гӮ„иЎҖз®Ўж–°з”ҹгҒ«й–ўгӮҸгӮӢиӘҝзҜҖеӣ еӯҗгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒҜгҒ“гҒ®mTORгӮ’йҒёжҠһзҡ„гҒ«йҳ»е®ігҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠдҪҚгҒ«гҒӮгӮӢPI3K-AktзөҢи·ҜгҒ®
жҙ»жҖ§еҢ–гӮ’йҳ»е®ігҒ—зҷҢзҙ°иғһгҒ®еў—ж®–гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«иЎҖз®Ўж–°з”ҹгӮӮйҳ»е®ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_186гҖ‘пҪһгҖҗIFI_187гҖ‘гҖҸ
йҖІиЎҢжҖ§гӮ„еҶҚзҷәгҒ®и…Һзҙ°иғһзҷҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒ®еҠ№жһңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ
гҒҷгҒ§гҒ«RECORD-1гҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒ
гҒқгҒ®зөҗжһңгӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№зҫӨгҒҜеҜҫз…§гҒ§гҒӮгӮӢгғ—гғ©гӮ»гғңзҫӨгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒ
з„Ўеў—жӮӘз”ҹеӯҳжңҹй–“гҒ®дёӯеӨ®еҖӨгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸдёҠеӣһгӮҠгҖҒдёӯй–“и§ЈжһҗгҒ§еҠ№жһңгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгӮҠ
и©ҰйЁ“гҒҢдёӯжӯўгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_188гҖ‘пҪһгҖҗIFI_189гҖ‘гҖҸ
гҒҫгҒҹгҒ“гҒ®и©ҰйЁ“гҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгӮӮеҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
гҒқгҒ®гӮөгғ–и§ЈжһҗгҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒ®зөҗжһңгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_190гҖ‘гҖҸ
гҒ“гӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒ2009е№ҙ3жңҲгҒ«зұіеӣҪгҒ§гҖҒ8жңҲгҒ«ж¬§е·һгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒ
дё–з•ҢгҒ®45гӮ«еӣҪгҒ»гҒ©гҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ2007е№ҙгҒ«гҖҢеҝғиҮ“移жӨҚеҫҢгҒ®жӢ’зө¶еҸҚеҝңжҠ‘еҲ¶гҖҚгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
2010е№ҙ1жңҲгҒ«гҖҢж №жІ»еҲҮйҷӨдёҚиғҪгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜ転移жҖ§и…Һзҙ°иғһзҷҢгҖҚгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰ
жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
(еҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢжүҝиӘҚжғ…е ұгҖҖhttp://bit.ly/Ky19c7)
гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠи…Һзҙ°иғһзҷҢгҒ®дәҢж¬ЎжІ»зҷӮгҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒ
гҖҢи…ҺзҷҢиЁәзҷӮгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғі2011е№ҙзүҲгҖҚпјҲйҮ‘еҺҹеҮәзүҲпјүгҒ§гӮӮгҖҒ
гҖҢиЎҖз®Ўж–°з”ҹйҳ»е®із„ЎеҠ№дҫӢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒmTORйҳ»е®іи–¬гҒ«гӮҲгӮӢ
дәҢж¬ЎжІ»зҷӮгҒ§з„Ўеў—жӮӘз”ҹеӯҳжңҹ間延長гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰ
жҺЁеҘЁеәҰBпјҲгӮЁгғ“гғҮгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶжҺЁеҘЁгҒҷгӮӢпјү
гҒ§иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и…Һзҙ°иғһзҷҢгҒ®дёҖйҖЈгҒ®жІ»зҷӮгҒ®дёӯгҒ§гҒ®гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒ®еҪ№еүІгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒ
еӨҡгҒҸгҒ®е ұе‘ҠгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_191гҖ‘пҪһгҖҗIFI_192гҖ‘гҖҸ
з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҹеә§и«ҮдјҡгҒ®иЁҳдәӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_193гҖ‘пҪһгҖҗIFI_194гҖ‘гҖҸ
дёҖж–№гҒ§гҖҒиЎ“еүҚгҒ®и…«зҳҚзё®е°ҸеҠ№жһңгҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢе ұе‘ҠгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_195гҖ‘гҖҸ
гҒҫгҒҹгҖҒгғҒгғӯгӮ·гғігӮӯгғҠгғјгӮјгҒӘгҒ©гҒ®иҖҗжҖ§з—ҮдҫӢгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гҒ•гӮүгҒ«гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒ«гӮӮиҖҗжҖ§гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮ№гғӢгғҒгғӢгғ–гӮ„гӮҪгғ©гғ•гӮ§гғӢгғ–гӮ’еҶҚеәҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮ
иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_196гҖ‘пҪһгҖҗIFI_197гҖ‘гҖҸ
гҒӘгҒҠгҖҒеҲқжңҹжІ»зҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгғҷгғҗгӮ·гӮәгғһгғ–гҒЁгҒ®дҪөз”ЁеҠ№жһңгӮ’гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғігҒЁ
жҜ”ијғгҒ—гҒҹRECORD-2и©ҰйЁ“пјҲClinicalTrial.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·NCT00719264пјүгӮ„гҖҒ
гӮ№гғӢгғҒгғӢгғ–гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹRECORD-3и©ҰйЁ“
пјҲClinicalTrial.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·NCT00903175пјүгҒӘгҒ©гҒ®з¬¬IIIзӣёи©ҰйЁ“гҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_198гҖ‘гҖҸ
гҒ•гӮүгҒ«дәҢж¬ЎжІ»зҷӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®з¬¬IIзӣёи©ҰйЁ“RECORD-4
пјҲClinicalTrial.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·NCT01491672пјүгӮӮиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ
гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№гҒҜе°ҶжқҘжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢи–¬еүӨгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
и…Һзҙ°иғһзҷҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзөҢеҸЈеҲҶеӯҗжЁҷзҡ„жІ»зҷӮи–¬гӮЁгғҷгғӯгғӘгғ гӮ№