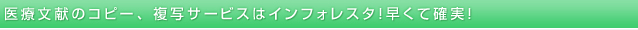еӨҡзҷәжҖ§зЎ¬еҢ–з—ҮгҒҜгҖҒи„ігӮ„и„Ҡй«„гҒ«иҮӘе·ұгҒ®гғӘгғігғ‘зҗғгҒҢжөёжҪӨгҒ—гҖҒ
зҘһзөҢзө„з№”гҒ®зӮҺз—ҮгҒЁзҘһзөҢзҙ°иғһгҒ®и»ёзҙўгӮ’иҰҶгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢй«„йһҳгҒӢгӮүгҒ®
и„ұй«„гӮ’гҒҚгҒҹгҒҷиҮӘе·ұе…Қз–«з–ҫжӮЈгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж„ҹиҰҡйҡңе®ігҖҒиҰ–зҘһзөҢзӮҺгҖҒйҒӢеӢ•йә»з—әгҒӘгҒ©гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
欧зұігҒ§гҒҜжӮЈиҖ…ж•°гҒ®еӨҡгҒ„з–ҫжӮЈгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӣҪеҶ…гҒ§гҒҜгҒҠгӮҲгҒқ14000дәәгҒ®
жӮЈиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®зү№е®ҡз–ҫжӮЈгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒӮгӮӢеһӢгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҶҚзҷәеҜӣи§ЈеһӢгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒеҶҚзҷәгҒ®дәҲйҳІгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘиӘІйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_170гҖ‘гҖҸ
иҝ‘е№ҙжӮЈиҖ…ж•°гҒҜеў—еҠ еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒ—гҒҰ欧зұіеһӢгҒ®
гғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒӘгҒ©гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_171гҖ‘гҖҸ
---------------------------------------
в—Ҷ гғ•гӮЈгғігӮҙгғӘгғўгғүпјҲFingolimodпјүпјҲFTY720пјү
---------------------------------------
еҜӣи§ЈгҒЁеҶҚзҷәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷз—…ж…ӢгҒ§гҒҜгҖҒеҶҚзҷәгҒ®дәҲйҳІгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘжІ»зҷӮжі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜдё»гҒЁгҒ—гҒҰгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіОІиЈҪеүӨгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜжӮЈиҖ…гҒ®иҮӘе·ұжіЁе°„гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒпј‘ж—Ҙпј‘еӣһгҒ®зөҢеҸЈжҠ•дёҺгҒҢеҸҜиғҪгҒӘи–¬еүӨгҒҢ
зҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮдәҲйҳІзҡ„жІ»зҷӮгҒҢе®№жҳ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғ•гӮЈгғігӮҙгғӘгғўгғүгҒҜгғӘгғігғ‘зҗғдёҠгҒ®гӮ№гғ•гӮЈгғігӮҙгӮ·гғіпј‘вҖ•гғӘгғій…ёеҸ—е®№дҪ“гӮ’йҳ»е®ігҒ—гҖҒ
жң«жўўиЎҖж¶ІдёӯгҒ®гғӘгғігғ‘зҗғгҖҒзү№гҒ«TгғӘгғігғ‘зҗғж•°гӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰ
е…Қз–«жҠ‘еҲ¶гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғӘгғігғ‘зҗғгҒ®дёӯжһўзҘһзөҢгҒёгҒ®жөёжҪӨгҒҢйҳ»е®ігҒ•гӮҢзҘһзөҢгҒ®зӮҺз—ҮгҒҢжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгӮӢиЁігҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_172гҖ‘пҪһгҖҗIFI_175гҖ‘гҖҸ
дә¬йғҪеӨ§еӯҰгҒ§еҶ¬иҷ«еӨҸиҚүгҒӢгӮүзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гӮӮж—Ҙжң¬гҒ®иЈҪи–¬дјҒжҘӯгҒҢ
зү№иЁұгӮ’жүҖжңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеӣҪз”ЈгҒ®и–¬еүӨгҒ§гҒҷгҖӮ
еҶ¬иҷ«еӨҸиҚүгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢIsaria SinclairiiгҒ®еҹ№йӨҠж¶ІгҒӢгӮүеҚҳйӣўгҒ•гӮҢгҖҒ
е…Қз–«жҠ‘еҲ¶еҠ№жһңгҒҢзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_176гҖ‘гҖҸ
зҸҫеңЁгҒҜIsaria Sinclairiiз”ұжқҘгҒ®зү©иіӘгҒ§гҒӮгӮӢгғһгӮӨгғӘгӮӘгӮ·гғіпјҲMyriocinпјүгҒ®
ж§ӢйҖ еӨүжҸӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҢ–еӯҰеҗҲжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“еҲқи…ҺиҮ“移жӨҚеҫҢгҒ®жӢ’зө¶еҸҚеҝңгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ
еҠ№жһңгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҡй–ӢзҷәгҒҜдёӯжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеӨҡзҷәжҖ§зЎ¬еҢ–з—ҮгҒёгҒ®е…Қз–«жҠ‘еҲ¶жІ»зҷӮгҒҢеӢ•зү©е®ҹйЁ“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮ
зўәиӘҚгҒ•гӮҢгҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_177гҖ‘гҖҸгҖҒ
欧зұігҒ§еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘиҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®зөҗжһңгғ—гғ©гӮ»гғңгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе№ҙй–“гҒ§еҶҚзҷәзҺҮгӮ’50пј…дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгҒҹгҒЁ
е ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷ(ClinicalTrials.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·гҖҖNCT00234540)гҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_178гҖ‘гҖҸ
2009е№ҙгҒ«зөӮдәҶгҒ—гҒҹгғ—гғ©гӮ»гғңгӮ’еҜҫз…§гҒЁгҒ—гҒҹFREEDOMSи©ҰйЁ“гҖҒ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_179гҖ‘гҖҸ
гҒҠгӮҲгҒігӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіОІгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹTRANSFORMSи©ҰйЁ“
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_180гҖ‘гҖҸ
гҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒӘзөҗжһңгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_181гҖ‘гҖҸ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮ第IIзӣёи©ҰйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_182гҖ‘гҖҸгҖҒ
2010е№ҙгҒ«зөӮдәҶгҒ—гҒҹи©ҰйЁ“гҒ§гҒҜ171з—ҮдҫӢгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰе№ҙй–“еҶҚзҷәзҺҮгҒҢ
гғ—гғ©гӮ»гғңзҫӨгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰ49пј…жёӣе°‘гҒ—гҒҹгҒЁе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зөҗжһңгҒҜгҒҫгҒ и«–ж–ҮгҒЁгҒҜгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгӮҰгӮЁгғғгғ–гғҡгғјгӮёгҒ§гҒ®гҒҝ
иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮпјҲhttp://bit.ly/IFijkKпјү
пјҲClinicalTrials.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·NCT00537082пјү
гҒҫгҒҹгҒқгҒ®еҫҢгҖҒжӢЎеӨ§и©ҰйЁ“гӮӮе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ2012е№ҙпј”жңҲгҒ«зөӮдәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲClinicalTrials.govзҷ»йҢІз•ӘеҸ·NCT00670449пјү
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүгҖҒ2010е№ҙгҒ«гғӯгӮ·гӮўгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒ
欧зұіеҗ„еӣҪгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁдё–з•ҢгҒ®50гғ¶еӣҪд»ҘдёҠгҒ§жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮ2011е№ҙпјҷжңҲгҒ«гҖҢеӨҡзҷәжҖ§зЎ¬еҢ–з—ҮгҒ®еҶҚзҷәдәҲйҳІгҒҠгӮҲгҒіиә«дҪ“зҡ„йҡңе®ігҒ®
йҖІиЎҢжҠ‘еҲ¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңүеҠ№жҖ§гҖҚгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢиЈҪйҖ жүҝиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲеҢ»и–¬е“ҒеҢ»зҷӮж©ҹеҷЁз·ҸеҗҲж©ҹж§ӢжүҝиӘҚжғ…е ұгҖҖhttp://bit.ly/JDnxS6пјү
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ•гӮЈгғігӮҙгғӘгғўгғүгҒ®еҠ№жһңгҒҜгҖҒжҠ•дёҺгҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰ
иЁјжҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
дёҖж–№гҒ§гҖҒйҒ©еҝңжқЎд»¶гӮ’иҖғж…®гҒ—гҖҒдёҖж¬ЎйҒёжҠһи–¬гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғӯгғіОІеҫҢгҒ®
дәҢж¬ЎйҒёжҠһи–¬гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮӢж„ҸиҰӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡгҖҗIFI_183гҖ‘гҖҸ
зөҢеҸЈеӨҡзҷәжҖ§зЎ¬еҢ–з—ҮжІ»зҷӮи–¬гҖҖгғ•гӮЈгғігӮҙгғӘгғўгғү