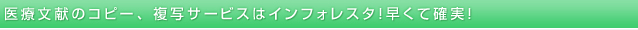これまで2回にわたりご紹介してきましたように
10/12/15配信【解説】新しい抗凝固剤 Part.2
10/11/17配信【解説】新しい抗凝固剤 Part.1
投薬管理が難しく、
患者さんのQOLにも影響を与えているワルファリンに代わる
抗凝固剤が求められています。
心房細動に伴う血栓予防に有効なワルファリン(経口)は、
定期的にプロトロンビン時間国際標準比(PT-INR)の測定が必要であり、
採血の必要や食物の影響などを考慮し、患者さんに適した投薬が必要でした。
こうした点からビタミンK非依存性の抗トロンビン剤や
Xa阻害剤が登場してきました。
『参考文献:【IFI_137】』
この程、Xa阻害剤であるアピキサバンの大規模臨床試験の
結果が報告されましたので、今後臨床の現場での適用が期待されています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
◆ アピキサバン(Apixaban)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xa阻害剤は、プロトロンビンからトロンビンへの合成を促進する第Xa因子を
阻害することにより、トロンビンの合成を阻害する作用を持っています。
中でもアピキサバンは、選択的・可逆的抗Xa阻害剤で、
Xa因子の遊離型とプロトロンビナーゼ複合体結合型の両方を阻害します。
また完全化学合成剤であるため、性状が均一で薬物動態も
容易に予測することが可能です。
『参考文献:【IFI_138】~【IFI_140】』
ワルファリンが、投与後治療域にまでその濃度が達するのに1週間程度を
要していたのに対し、アピキサバンは速効性があり4時間以内に血中濃度が
ピークに達し、およそ半日の半減期を示します。
このため一日2回の経口投与が必要です。
『参考文献:【IFI_141】』
アピキサバンの効果については、まずアスピリンと比較した
AVERROES試験が行われています。
その結果は脳卒中と全身性塞栓症ではアピキサバンが有効であるが、
大出血の予防については同等であったというものです。
(ClinicalTrials.gov臨床試験番号 NCT00496769)
『参考文献:【IFI_142】~【IFI_143】』
続いて非常に大規模な臨床試験であるARISTOTLE試験が行われました。
(ClinicalTrials.gov臨床試験番号 NCT00412984)
これは直接ワルファリンと比較したもので、日本の40施設を含む
世界39ヶ国1,034施設が参加し、患者さんの数は18,201人に上っています。
二重盲検ランダム化比較試験(第III相)であり、中央値で1.8年間追跡され、
ITT解析が行われています。
結果は、脳卒中と全身性塞栓症では21%、大出血では31%、
全死亡では11%それぞれリスクが減少している、というものです。
これにより、ワルファリンに対して非劣性であるばかりではなく、
優位性が示されたことになります。
これは2011年8月の欧州心臓病学会で発表されたのですが、
総合医学雑誌New England Journal of Medicineの電子版にすぐに掲載され、
9月には印刷版でも出版され話題となりました。
『参考文献:【IFI_144】』
欧州では2011年5月には27ヶ国で承認され、米国でも申請予定です。
日本では未承認ですが、「心房細動患者における脳卒中予防」という薬効で
申請予定であり、2013年には上市されるものと予測されています。
またARISTOTLE-Jと名付けられた第II相試験(患者数222人)
(ClinicalTrials.gov臨床試験番号 NCT00787150)が日本でも行われており、
ARISTOTLE試験と同様の結果が出ています。
『参考文献:【IFI_145】』
これらより、日本に置いても今後の臨床応用が期待されています。
『参考文献:【IFI_146】~【IFI_149】』
ワルファリンに代わる新しい抗凝固剤 Part3 Xa阻害剤 アピキサバン